こんにちは、Yです。
投手の守備の中で大切ですが、忘れがちなプレーがカバーリングです。
大切だとわかっているのですが、結構な頻度で忘れてしまうことがありました。
確実に1つアウトを取れるプレーをカバーリングがうまくいかないことで落してしまうことや、カバーリングがあれば進塁を止めることができたということはたくさんありました。
そういった一つ一つの積み重ねが強いチームと弱いチームの違いだと感じています。
カバーリングとは、「連携プレー」です。
つまり、一人でうまくなることはできないし、一人が上手くてもだめなのです。
まわりの野手の動きを考えて、ランナーの状況や試合展開なども踏まえて、動きを考えることでカバーリングの精度は上がっていきます。
今回はレベルの高い投手になるために確実に抑えておきたいカバーリングに関する考え方を解説します。
カバーリングについて課題を持っている方は、是非最後まで記事を読んでみてください。
とにかくボールに向かって走れ!!
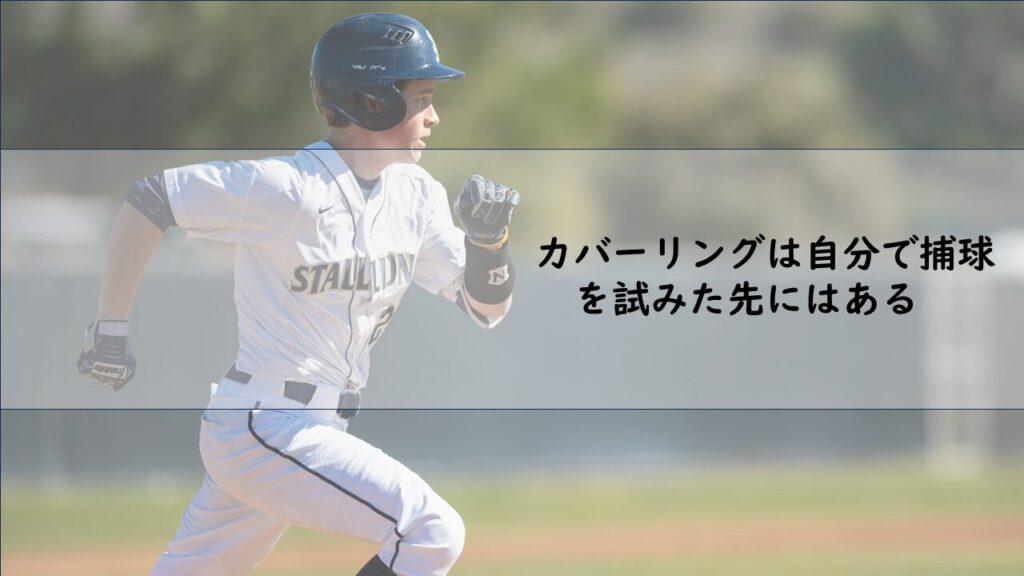
カバーリングには2つのパターンがあります。
①打球処理の延長でカバーリング
②返球が逸れた時のカバーリング
①は捕球に向かった結果、カバーリングに切り替えるパターンです。
捕球に向かった結果、同じくボールに向かってきた野手が捕球し送球することで、捕球した野手の守るポジションへのカバーリングするものです。
例えば、ファースト側のバント処理に向かった投手とファーストですが、結果ファーストが捕球したとすれば、1塁ベースが空いてしまいます。
セカンドがカバーリングに入ることもありますが、ファースト側に走っている投手のほうが早いと判断すれば、投手がそのまま1塁ベースへ走り、ファーストからの送球をランニングキャッチして処理することでアウトをとることができます。
プロの試合などでもよく見かけるプレーですが、一見簡単にやっているように見えるプレーですが、やってみるとなかなか難しいです。
気を付ける点は以下のとおりです。
- 打たれた瞬間は捕球するために全力で走る
- 捕球に向かっているところから切り替えてファーストへ向かうタイミング
- それをしっかりまわりに知らせる声
- 送球する際の連携プレー
①については、意識の問題です。
打たれた瞬間に全力で走ることを心掛けてください
いい加減に走ってしまうと、ファーストが捕球した結果、投手もセカンドもファーストに間に合わないということが起こってしまいます。カバーリングまでにランナーとの競走に勝てるように全力で走りましょう。
②~④は普段の練習で野手との意思疎通により精度を上げることができます。ノックやケースバッティングなどで練習し、カバーリングに関する意見交換をしっかりする機会を大切にしてください。
連携の練習では特に「声」を出す練習を意識してください
声でお互いの思いを共有できないと、お互いが捕球を任せてしまいだれも捕球にいかないという悲劇が起こってしまいます。
自分がカバーリングに回るのであれば、
「こっち!!」
と大きな声でとボールを送球してほしいところを呼ぶ練習をしましょう。
まずはじめのワンプレーから気を抜かずに取り組むことが大切です。打球に対して全力で走ることが後のカバーリングを成功させることにつながっていくのです。
打たれて悔しい気持ちは後回し
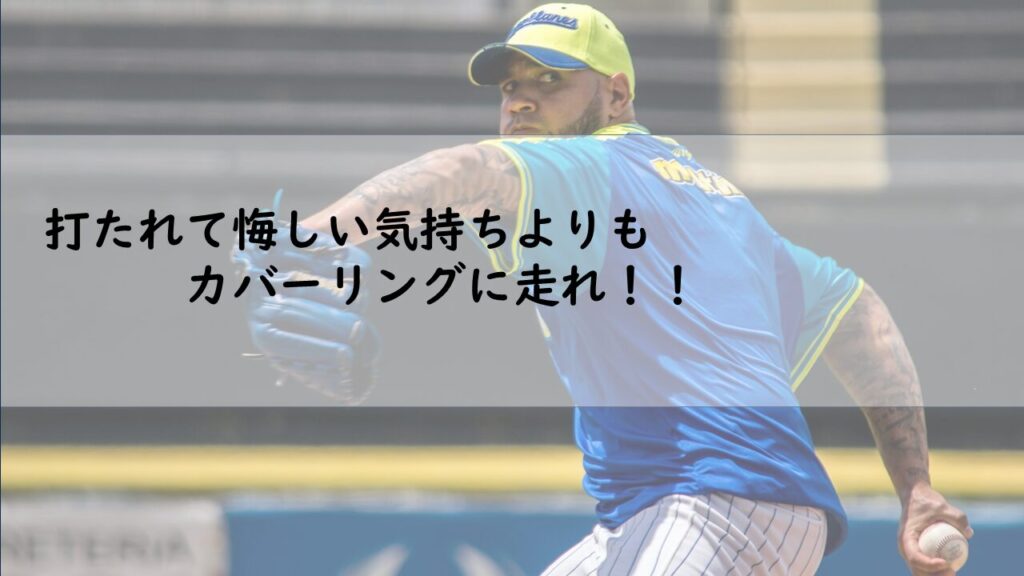
パターンの2つめは返球が逸れた場合のカバーリングです。
打球が外野に抜けた場合に、外野からの返球が逸れた場合すぐにカバーできるように、返球先のベースの少し後ろに備えるというのが基本です。
ランナーやアウトカウントや点差などの状況判断で返球先を想定してカバーリングに動く必要があります。
投手がカバーリングに入ることが多いのは、サードかホームベースが多いです
ファーストは基本的に外野へ抜ける打球でカバーリングは不要です。
2塁ベースはセカンドとショートで対応することが多く、どちらかがカットに入る場合はファーストが対応することもあります。
そのため、3塁ベースやホームベースへのカバーリングへの対応がメインになります。
例えば、ランナー2塁の状態から外野へ抜けるヒットを打たれた際は、バックホームへの送球を想定してホームの少し後ろで返球の延長線上にカバーに入ります。
この場合、状況によってはサードで止まる可能性があり、サードへの返球になることも頭に入れてランナーの動きに注意しつつカバーリングに動く必要があります。
気を付ける点は以下のとおりです。
- 打たれた瞬間にがっかりしてカバーリングのことを忘れない
- カバーリングに走りながら打球の行き先をしっかり確認する
- 少し距離をあけた位置でカバーする
- 送球が逸れてカバーに飛んできた場合、体を張ってとめる
①について、「そんなやつはいない」と反論されるかもしれませんが、残念ながらカバーリングを忘れるバカ者はいます。
打たれたらすぐに「カバーリング!!」
というしっかりした意識付けとまわりからの声掛けで改善可能です。
②、④については練習の中で慣れにより精度が上がってくるのではないでしょうか。
③については、大切なのは意識として「自分が思っているより少し距離をとって守る」くらいの感覚でいいのかなと思っています。近すぎると、カバーの役割が果たせず、一緒に逸らしてしまう危険性があります。
バッターランナーがいることを考えれば確実に捕球して1つでも進塁を止めたいところです。
経験上、投手が打たれた瞬間にカバーリングを忘れてしまって動けないということが一番の障壁になると感じます。
スコアリングポジションにランナーがいる場合、外野へ抜けたら投手はカバーリングが必要と頭にインプットすることが大切です。
フォーメーションは練習の賜物
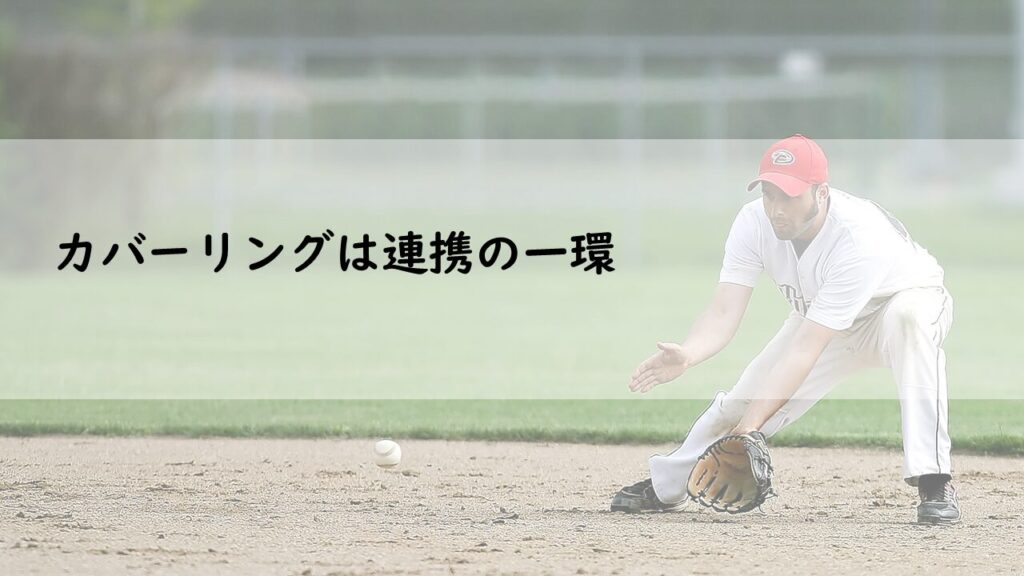
前項、前々項でご紹介したカバーリングのパターンではどちらとも、野手との連携がとても重要です。普段からフォーメーションの練習でお互いの動きを確認しておきましょう。
前々項のパターンでは、互いに捕球に向かった場合どちらかが優先的に処理するかを決めておくと、速い段階で切り替えてカバーリングに入ることができます。
逆にこの取り決めがあいまいで、お互いが最後まで捕球に向かってしまうと、
選手同士で接触して怪我の危険
があります。
例えば、前者のカバーリングについては、後ろにいる選手が主導権をとって判断することが一般的です。
1塁側のバントの場合、ファーストと投手だとファーストから主導権を握って声を出して判断する場合が多いです。
後ろのポジションから俯瞰的に見てどちらが対応することが良いのかを判断して大きな声で指示することでコントロールできます。
練習から互いの特徴などを理解して連携を取り合っておくことで、本番でも自信をもって指示をすることができます。
前項のパターンでは、全体ノックでアウトカウントやランナーを想定することにより、返球する場所をお互いに確認しておくと、打球の強さ・方向・ランナーの状況により送球先を早い段階で特定できれば、カバーに走る場所を決めて余裕を持ってカバーリングに向かうことができます。
逆に連携がしっかりしていないと、
・野手ごとに送球先の認識がバラバラになり返球が最短距離で帰ってこない
・カバーリングに走っていたところと違うところに返球が来る
といったことが起こってしまいます。
例えば、返球指示の場合、球場全体俯瞰的に見ることができるキャッチャーが指示するのが一番効率的です。
打たれた時は、一端キャッチャーの近くまで寄ってどのような指示を出しているかをよく聞いた上で、カバーリングに入る位置を想定することでスムーズにカバーリングに入ることができます。
また、練習の時からキャッチャーの考え方を学び理解することで、本番でのランナーの状況・打球の勢い・飛んだ方向からどのような返球指示になるかをある程度想定し、カバーリングに入る場所へいち早く向かうことができます。
投手にとってフォーメーションは後になりがちな練習メニューですが、良い投手ほどカバーリングにも余念がありません。普段から野手と連携をとって具体的なケースを想定したカバーリングの練習を大切にしてください。
大切なプレーですが、結構忘れる人います
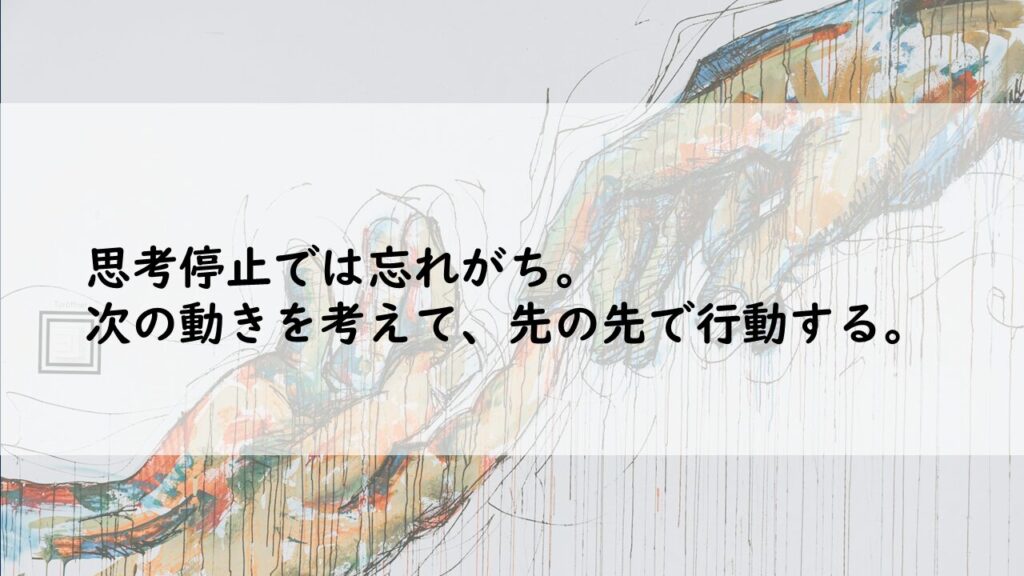
カバーリングについて一番にお伝えしたいことは、
本当に忘れてしまう人が多いということです
疑問に思う方もいるかもしれませんが、実際マウンドに立つと打たれた後は野手にお任せ思考の投手は多いです。
捕球の際のカバーリングでも、
投球しました
→バントされました
→ボールを追いかけました
→ファーストが捕球しました
→(自分の仕事は終わりました。)
となることが多いです。(もっと言うとはじめからファーストに全て任せて自分はマウンド付近から動かない投手は多いです)
返球へのカバーリングの場合は、打たれた瞬間に気持ちが動揺してしまい、まわりが見えなくなってその場でへこんでしまい、カバーリングに走ることを忘れるといったことが多々起こります。
自分はそうはならないとお考えのあなたも絶対に経験します。
サード側のバント処理の際、サードに処理してもらい投手はサードにカバーリングが必要な場面でカバーリングを忘れた結果、がら空きのサードにセカンドランナーからの進塁を許すということは良くある話です。
また、外野に抜けた打球のバックホーム返球が大きく逸れてしまい、本来投手がカバーリングに入っていれば1人目のランナーの生還だけで済んだものが、カバーリングを忘れたことで、2人目、3人目と生還するランナーが増えたケースもたくさんあるのではないでしょうか。
局面によっては、カバーリングの忘れが試合の流れを大きく左右する可能性もあることを肝に銘じなければなりません。
それほど重要なプレーが未だによく忘れられるプレーであるということも忘れてはいけません。
本人の意識付けはもちろんのことですが、野手から声をかけて動かすということも大切な連携プレーです。
まとめ
とにかくボールに向かって走れ!
はじめのワンプレーから気を抜かずに取り組むことが大切です。打球に対して全力で走ることが後のカバーリングを成功させることにつながっていくのです。
打たれて悔しい気持ちは後回し
カバーリングは投手が打たれた瞬間に頭から飛んでしまって動けないことが一番の問題だと感じます。スコアリングポジションにランナーがいる場合、外野へ抜けたら投手はカバーリングが必要と頭にインプットすることが大切です。
フォーメーションは練習の賜物
カバーリングの練習は後になりがちですが、試合の流れを変えるプレーになることもあるので気が抜けません。良い投手ほどカバーリングにも余念がありません。普段から野手と連携をとって具体的なケースを想定したカバーリングの練習を大切にしてください。
大切なプレーですが忘れる人がいます
実際マウンドに立つ投球に気をとられてカバーリングが抜けることが起こりがちです。本人の意識付けはもちろんのことですが、野手から声をかけて動かすということも大切な連携プレーです。
冒頭でも述べましたが、カバーリングは大切なプレーですが忘れられがちで、まわりとの連携が重要なプレーなので一人で上手くなることは難しいプレーです。
普段の練習時より、具体的な場面を想定した練習により連携プレーの精度を上げることが大切です。
全体ノックやケースバッティング、紅白戦などの守備機会を使ってまわりの野手との連携プレーの時間を大切にしてください。
あなたの投手への挑戦を応援しています。

コメント